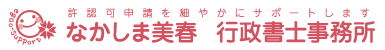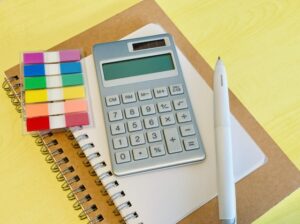あなたの「困った」を「相談してよかった」に変える行政書士・相続コンサルタントのなかしま美春です。
全33回のコラム、第15回をお届けします。
この連続コラムでは、「相続でトラブルになりやすいこと」、そして「今できること」について、わかりやすくお伝えしていきます。
このコラムが、相続について考える小さなきっかけとなり、
そして「家族で話す」「書き残す」という第一歩につながることを願って――
ぜひ最後までお付き合いください。
(全33回の一覧は>>こちら)
【連続❢相続コラム】第15回:「借りている土地」「貸している土地」がある

写真はイメージです
「うちの畑は昔から親戚に貸している。詳しくは分からないけど、今まで問題になっていないから、これからも特に問題ないはず」
「祖父の代から借りてる土地だから、これからも同じ条件で使えるだろう」
「貸している土地は毎年使用料をもらっているし、特に問題は感じていない」
――そう思っている方も少なくないかもしれません。
けれども、この「借りている土地」「貸している土地」、相続が発生すると思わぬ形で相続人の肩に重くのしかかることがあります。
口約束でも有効
民法上、契約は「当事者同士の合意」で成立します。(民法522条・契約の成立要件)
つまり「貸します」「借ります」と当事者同士で合意すれば、それだけで契約は成立します。
書面がなくても、立派に法律的な効力を持つのです。
なぜトラブルになるのか?
誰かが亡くなり相続が始まると、被相続人(亡くなった人)の【権利】や【義務】もすべて相続人へ引き継がれます。
先ほど書いたとおり、「口約束」でも法律上は契約として有効です。
しかし、契約書がなく、相手方とのやり取りが曖昧なままだと…
「本当に借りていた(貸していた)のか?」
「契約内容はどうなっていたのか?」
「借りる期間は何年?」
「地代はいくら? いつ払う?」
「返すときは更地にして返すのか?」
などなど、相続人同士や相手方との間にトラブルが生じる可能性があります。
特に、借りている側・貸している側の相続人同士が面識のない場合は、話し合いがスムーズに進まず、争いに発展するケースも少なくありません。
裁判になった場合
もしトラブルが裁判にまで発展した場合、たとえ口約束であっても当事者間に意思の合致があったことが認められれば、契約そのものは有効と判断されるケースが圧倒的に多いです。
しかし、契約内容(契約期間・地代や使用料の金額・支払い方法・返還条件など)を裏付ける資料や証拠が不足していると、裁判所は周囲の状況や地域の慣習、合理的な取り決めを基準に判断せざるを得ません。
そのため、当事者が本来望んでいた条件とは異なる形で結論が下される可能性があり、結果的に地主・借主のいずれかが大きな不利益を被るおそれがあります。
行政書士の立場からの解決策
こうした問題を防ぐためには、まず 「契約関係の【現状把握】をしておくこと」 が大切です。
✅ 借りている(貸している)土地の範囲・条件を整理する
✅ 契約書がない場合は、新たに契約書を作成しておく
✅ 契約内容について、相続人にわかるようにエンディングノートに記録しておく(※)
(※)エンディングノートには法的効力がないため「契約の証明書類」として認められるわけではありません。
契約内容が明確でないと、相続人は「借りているはず」「貸しているはず」と主張しても証拠がなく、解決までに時間や費用がかかります。
ここにも注意!
❗借地・借家契約など土地利用の契約は、相続の際に特に注意が必要です。
① 契約書がない
→ 相続人が内容を証明できず、トラブルに発展するリスク大
② 相手方が分からず、連絡がつかない
→ 交渉の窓口が不明確になり、相続手続きが進まない
③ 地代や使用料の支払いが不明確
→ 相続人が「未払いを請求された」「払いすぎていた」などで大混乱
【「困らない相続」がいちばん!】
いかがでしたか?
昔からの土地の「借りている・貸している」は、口約束のまま放置されているケースが非常に多いです。
だからこそ、
✅今の契約状況を把握して整理すること
✅できれば、今からでも契約書を交わすこと
✅相続人に分かるように記録しておくこと
これらが残された家族を守る大切な準備になります。
「うちの場合は、どう整理したらいいの?」と不安に思った方は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
✨ エンディングノートは、残される家族を笑顔にする魔法です ✨
✨ 契約の「見える化」が、家族の安心につながります ✨
どうか手遅れになる前に、お早めに「契約関係」を確認【現状把握】をしてみてくださいね。
「あれ?私の場合はどうなんだろ?」と気になった方へ
このコラムの執筆にあたり、一般社団法人 相続診断協会の「相続診断チェックシート」のチェック項目の一部を参考にさせていただきました。
「相続診断チェックシート」を使えば、ご自身の状況を診断することができます。
30個あるチェック項目に答えるだけで、ご自身の現状がわかり、「このまま何もしないと、何が問題になるのか」をあぶり出すことができます。
ご興味のある方は、「「相続診断チェックシート」診断希望」と、お気軽に当事務所までご相談ください(^^)