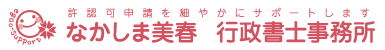6つの業務案内
works
01

建設業許可申請
works
02
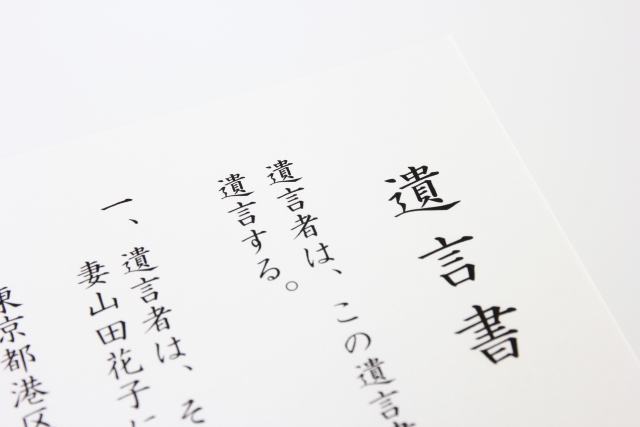
相続・遺言・終活
works
03

建設キャリアアップシステム
works
04

外国人ビザ申請
works
05

産業廃棄物収集
運搬業
(積替・保管除く)
許可申請
works
06

宅地建物取引業免許申請
works
01
建設業許可申請
建設業許可は、どんな場合に必要?!
⇒ 建設業許可が必要になるのは「大きな工事」と「公共工事」を請け負う場合です。
1.規模の大きな工事を請け負うとき
建設業許可は、「軽微な建設工事」だけを行う場合には不要とされています。
「軽微な建設工事」とは?
★建築一式工事の場合
工事1件の請負金額が 1,500万円未満の工事 又は 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
このどちらかに当てはまれば「軽微な建設工事」となります。
★建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負金額 500万円未満の工事
「軽微な建設工事」だけを行う場合には、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。
2.公共工事に入札したいとき
建設業許可がなければ、そもそも公共工事に入札することが出来ません。
流れとしては、(1)建設業許可を受ける (2)経営事項審査を受ける (3)各自治体や省庁の入札参加資格を得る ことになります。
建設業許可を新規に取得するための要件は5つあります。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに一定の資格や経験のある技術者を専任で設置できること
③誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと
建設業許可の有効期限は5年間です。毎事業年度(決算期)ごとに決算変更届出書を提出し、5年ごとの建設業許可の更新手続き(許可有効期間満了日前30日までに提出)が必要です。
●新たに建設業許可を取得されたい方
●将来的に建設業許可の取得をお考えになっている方
●取引先、元請業者様から許可を取得するように言われた方
●会社設立と同時に建設業許可を取得されたい方
●経営事項審査を受けて公共工事を受注したい方
●建設業許可を取得して対外的な信用を高めたい方
建設業許可でお困りの方や、「実は建設業許可がないのに、500万円以上の工事をしてしまっていた・・・」など、建設業許可をとるのは無理かな?と諦めようとしている方は、諦める前に、なかしま美春 行政書士事務所にお問い合わせください。
★「解体工事」は要注意!!解体工事における「許可」と「登録」の関係性とは?
解体工事とは、建造物の取り壊し工事のことです。
解体工事業登録は、どんな場合に必要?!
解体工事を行うには、建設業の許可を持っているか、解体工事業の登録を受けていなければなりません。
解体工事を営もうとする場合は、元請か下請にかかわらず、工事の請負金額が500万円未満でも、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。営業所を置かない都道府県であっても、その都道府県で解体工事を行う場合はその都道府県を管轄する知事の登録を受けなければなりません。解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。
解体工事業登録をするための要件は2つあります。
①拒否事由に該当しないこと
②技術管理者を選任していること
●新たに解体工事業登録をされたい方
●現在、建設業「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行っており、「解体工事業」の業種追加をされたい方
解体工事業登録、建設業許可でお困りの方は、なかしま美春 行政書士事務所までお問い合わせください。
解体工事業登録と建設業許可との比較
| 解体工事業登録 | 建設業許可 | |
| 営業可能な工事 | 1件500万円未満の解体工事のみ | 1件500万円以上の工事も可能 |
| 施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
| 登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 | 全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県 |
| 営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省 | ||
| 登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
works
02
相続・遺言・終活
自筆証書遺言作成・公正証書遺言作成
「遺言」ってなに?!
生前に、自分の死後、誰にどのように遺産を分けるか等について指定しておくものです。遺言に書ける事項は民法で決められています。民法で規定されている書き方で正しく作成された遺言には、「法的な効力」があり、遺言を書いた方が亡くなった後にその効力を発揮します。
遺言書には、主に「2つの方式」があります。 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成
「遺言」とは、生前に、自分の死後、誰にどのように遺産を分けるか等について指定しておくものです。 遺言に書ける事項は民法で決められています。民法で規定されている書き方で正しく作成された遺言には、「法的な効力」があり、遺言を書いた方が亡くなった後にその効力を発揮します。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の良い点・悪い点
| 良い点 | 悪い点 | |
| 自筆証書遺言 | ・作成費用がかからない ・気軽に書ける ・書き換えが簡単 | ・発見されない危険性あり ・破棄、隠ぺいされる危険性あり ・不備により無効になる危険性あり ・家庭裁判所での検認手続が必要 (法務局で保管したものは検認不要) |
| オススメ! 公正証書遺言 | ・不備による無効がない ・公証役場で保管されるので安心 ・家裁での検認手続は必要ない ・死後の相続手続きが容易になる | ・公証役場に出向かなければならない ・作成費用がかかる ・証人2名が必要 |
無駄にならない遺言をつくるには?!
①気力・体力がある元気なうちに、「公正証書」で遺言をつくる!
②作った遺言を、書きっぱなしにせず、「定期的に見直し」する!
③「遺留分(※1)」のことも考えて、「付言事項(※2)」、「予備的遺言(※3)」を活用する!
④「遺言執行者(※4)」を決めておく!(未成年・破産者は遺言執行者になれません)
⑤「遺言があること」を周りの方に知らせておく!
(※1)遺留分・・・相続財産の一定割合を取得できる権利の事。遺言で財産の分配の割合を 決めていても、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分がある。
(※2)付言(ふげん)事項・・・財産の分け方以外に相続人に遺す言葉で、遺言者の気持ちや、財産を分けた理由、感謝の気持ちを自由に書くことができるが、付言事項には法的な効力はない。
(※3)予備的遺言・・・遺言書の中で「相続させる」と指定した推定相続人が自分よりも先に死亡する事を想定した補充規定(=予備的遺言)のこと。
(※4)遺言執行者・・・相続が起きた後、遺言に書かれた内容を実行する人のこと。
公証役場の手数料
公正証書遺言とは、公証役場に出向き作成してもらう遺言書をいいます。
公正証書により作成される遺言書で証人2人立会いのもとで作成され、公証役場で保管されます。
公正証書作成手数料(公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。)
| 遺言書に書く財産の額 | 公正証書作成手数料 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 1億円5,000万円まで | 56,000円 |
| 2億円まで | 69,000円 |
※公証役場への手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。
※祭祀承継者(墓を引き継ぎ法要をする者)を指定する場合は、11,000円が加算されます。
※遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、公正証書作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が必要となります。
当事務所に依頼するメリット
★必要書類をすべてご用意します
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や固定資産評価証明書などさまざまな書類が必要となります。
遺言書作成に必要な書類の作成、取り寄せをすべて行います。
★公証人との打ち合わせをします
公証人との打ち合わせにはある程度の法律知識も必要となります。
お客様の希望内容を可能な限り実現できる方法を提案します
★遺言作成のプロが文案作成をします
お客様のご希望、ご家族の負担、リスク、費用面、様々な点を考慮して、最善の遺言内容を提案します。
★証人2人の立ち合い費用も含みます
「証人」になることができない方
・未成年者
・遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族
・公証役場の職員など
・遺言書の内容を読めない、確認できない人
「遺言内容は親族や他人に知られたくない」「証人がなかなか見つからない」といった場合もご安心ください。当事務所の公正証書遺言作成サービスでは、証人2人の立ち合い費用も含めた報酬になっています。
★遺言執行もお手伝いします
遺言で「遺言執行者」として指定いただくことも可能です。
責任をもってお客様の遺言の内容を実現します。
★守秘義務があります
遺言書内容を他人に知られたくない場合もご安心ください。
行政書士には守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは絶対にありません。
works
03
建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステム(CCUS) とは?
建設キャリアアップシステムは、一言でいうと、各技能者(職人)の能力等を業界統一の基準で登録し、 「見える化」 (IDが付与されたICカードを交付)をするシステムです。 建設キャリアアップシステムでは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界統一の 基準で登録・蓄積されます。システムの活用により、技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる 環境を整備し、将来にわたって建設業界の担い手を確保することが一番の目的です。 2019年4月から本格運用を開始されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
↓
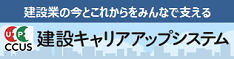
建設キャリアアップシステム(CCUS)
なぜ「建設キャリアアップシステム」を登録する必要があるの?
①【元請からの要請】現在、元請業者(ゼネコン含む)から下請業者に対し、建設キャリアアップシステムに登録するよう、通知等がされていること
②【外国人労働者雇用時は登録が義務】在留資格「特定技能」や、在留資格「技能実習」(2020年1月~適用)の外国人労働者を雇用とする場合は、雇用する建設会社の登録は必須の要件であること
③【経営事項審査への影響】官民が連携して推進するシステムなので、今後、経営事項審査や入札参加資格申請、建設業許可の確認資料として使用される可能性が高いこと
上記より、建設業キャリアップシステムの登録をしていない事業者様・技能者様は現場の入場や、公共工事の入札関連で出遅れる可能性も考えられますので、早々に登録することをお勧めいたします。
建設キャリアアップシステムのメリット
事業者のメリット
・技能者の就業状況等の確認が容易になります。
・ICカードにより、 現場の入退場管理の効率化できます。
・経営事項審査の加点対象になります。
技能者のメリット
・自分の技能レベルの証明が容易になります。
・就業現場に関わらず、適正な評価が受けられます。
事業者様からの依頼を受けた行政書士は、事業者登録、技能者登録のいずれもお手伝いをすることができます。
特に、技能者を多く雇用している事業者様では、登録作業にかなりの時間がかかると思われます。当事務所では、そのような事業者様の「事業者登録申請」、「技能者登録申請」のお手伝いをいたします。
登録申請には、インターネット申請、窓口申請の2つの方法があります。少しでも迅速な登録作業をすすめるために、当事務所では、インターネットを使用して申請いたしますので、全国どこの建設会社様からのご依頼もお受けできます。
なかしま美春行政書士事務所では
【事業者登録】代行申請
【技能者登録】代行申請
を承っております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
works
04
外国人ビザ申請
外国人が日本に入国または滞在するためには、当該外国人の日本での活動が、入管法で定められた「在留資格」に該当している必要があります。そうでなければ、不法滞在となり、刑罰や強制退去の対象になります。このような決まりごとが決められているのが出入国管理および難民認定法です。出入国管理および難民認定法は略して「入管法」とよばれています。
日本に在留する外国人は、決定された在留資格で認められる活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入、報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行って、法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍ら、それ以外の活動で収入、報酬を伴う活動を行おうとする場合には、資格外活動の許可を受けなければなりません。また、決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
●外国人を雇いたい。
●外国人が日本で会社を作りたい。
●外国人妻や夫が日本人配偶者を亡くした場合、離婚した。
●在留期限が切れてしまった、もうすぐ切れてしまうので延長したい。
●帰化をして、日本の国籍が欲しい。
●ずっと日本に住んでいるので永住権が欲しい。
●国際結婚をしたい。
●就労できる在留資格へ変更をしたい。
●海外にいる家族を日本に呼び寄せたい。
外国人の在留資格についてお困りの方は、なかしま美春 行政書士事務所へお問い合わせください。
works
05
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)許可申請
「産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)」を営もうとする方は、個人・法人に限らず、都道府県知事 又は政令市の許可を受ける必要があります。
必要な事前講習
許可申請に際して、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の 写しが必要になります。(許可申請時には、「原本」持参)事前に必ず受講しておいてください。 ※開催日程が決まっており、すぐに受講できない場合がありますので、ご注意ください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
[https://www.jwnet.or.jp]
講習会の修了証は、全ての都道府県・政令市での許可申請に使用できますので、講習会の場所が許可 申請先の都道府県・政令市と異なっても問題はありません。
許可を受けるための必須要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、下記の5つの要件を備えている必要があります。
【産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件】
- 講習会を受講していること。(前項にて記載のとおり)
- 運搬車両・容器・駐車場の使用権限などが整っていること。
- 適切な事業計画があること。
- 経理的基礎があること。
- 欠格要件に該当しないこと。
あらゆる許認可は「ヒト・モノ・カネ」といいますが、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)も 例外ではありません。 上記5つの要件が整っていること、また継続して要件を満たしていることを色々な書類で証明し、 「新規許可・許可更新・変更届」等を提出する必要があります。
works
06
宅地建物取引業免許申請
不動産業を営むためには、「宅地建物取引業免許」が必要です。
宅地建物取引業を開業するためには、行政への免許申請手続きと並行して、公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会等の協会へ、加入申し込みを行わなければなりません。
宅地建物取引業を開業するまでの準備として「営業保証金」を法務局に供託することが義務づけられていますが必要となる供託金の金額は、主たる事務所1,000万円とされていて、かなり高額です。
法務局に1,000万円を供託するかわりに、「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会」等の協会に加入することで、弁済業務保証金分担金の60万円で済みます。
断然、協会(ハトマークorウサギマーク)に加入される事業所さんが多いです。
宅地建物取引業とは?
国土交通大臣免許or都道府県知事免許
宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許の有効期間
宅宅地建物取引業の免許の有効期間は「5年間」です。
有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
標準処理期間
※都道府県知事免許については各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課 へご照会下さい。