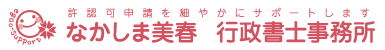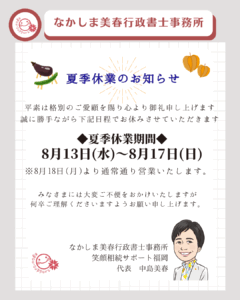あなたの「困った」を「相談してよかった」に変える行政書士・相続コンサルタントのなかしま美春です。
全33回のコラム、第10回をお届けします。
この連続コラムでは、「相続でトラブルになりやすいこと」、そして「今できること」について、わかりやすくお伝えしていきます。
このコラムが、相続について考える小さなきっかけとなり、
そして「家族で話す」「書き残す」という第一歩につながることを願って――
ぜひ最後までお付き合いください。
(全33回の一覧は>>こちら)
【連続❢相続コラム】第10回:配偶者や子ども以外の人や団体に財産を渡したい

写真はイメージです
「お世話になった友人に少しでも財産を渡したい」
「長年支えてくれた介護職員さんに感謝を伝えたい」
「子どもも親族も居ないので、遺産は〇〇団体に寄付したい」
私たちにとって、こうした想いはとても自然なものです。
しかし残念ながら、きちんとした対策をしておかなければ、それらの想いが叶うことはほとんどありません。
それどころか、親族がまったくいない場合、何も準備をしていなければ、あなたの財産はすべて「国のもの」になってしまう可能性があります。
そこで今回は「想いをカタチにする」ためにできる準備について解説します。
「ちゃんと感謝を伝えたかったのに…」
「本当は別の人に遺したかったのに…」
――人生の最後に後悔を残さないために、ぜひ今回のコラムを活用してくださいね。
確実に想いを実現するには:やっぱり「遺言書」
まず前提として知っておいていただきたいのは、法定相続人「以外」は、原則として“相続する権利”が「ない」ということです。
もし法定相続人が一人もいない場合は、その方の財産は最終的に「国のもの」になります(国庫に帰属します)(※1)。
ですから、相続人「以外」の人や団体に財産を遺したい――
そう強く願うなら、一番確実でおすすめの方法は「遺言書の作成」です。
遺言書があることで、
✅ 法定相続人「以外」の方への遺贈(いぞう)ができる
✅ 贈る相手や財産内容を具体的に指定できる
✅ 自分の想いを「附言事項」として添えることができる
「どうして、そうしたいと考えたのか」その想いを遺言書の「附言事項(ふげんじこう)」に記しておけば、他の相続人の理解も得られやすくなり、相続トラブルの回避にもつながります。
附言事項とは、法的な効力はないものの、遺言者の「想い」や「背景」を自由に伝えられる文章(手紙)部分のことです。
付言事項の例
「〇〇さんには、闘病中の介護でお世話になりました。その感謝を込めて、財産の一部を遺贈します」
「私の人生を支えてくれた感謝を込めて、△△団体に財産の一部を寄付します」
なお、遺言書を作成する際は、「遺留分(※2)」にも配慮しましょう。
(※1)残余財産の国庫への帰属(民法第959条)
日本の民法では、相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)がおらず、かつ遺言もない場合、特別縁故者への分与手続きを経てもなお相続財産が残るとき、その残余財産は最終的に国庫に帰属します。
(※2) 遺留分(いりゅうぶん)
遺産を相続する一定の相続人に対して最低限保証されている遺産取得分のこと(民法第1042条)
(参考):(民法第906条)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
生前贈与という手段も
「まだ元気なうちに財産を渡したい」と考える方は、生前贈与という方法もあります。
生前贈与のメリット
- 遺言と違い、死後を待たずに渡せるので、受け取りを見届けられる
- 感謝や想いを相手に直接伝えられる
- 使い道を見届けられる(特定の用途、学費や医療費などに限定した贈与も可能)
生前贈与の方法
生前贈与には、書面による「贈与契約」と口頭での贈与(手渡し等)があります。
当事務所では、証拠が残りトラブル防止になるため、書面による「贈与契約」をオススメしています。
⚠ 贈与で注意すべきこと
① 贈与税の課税対象になることがある
②寄付先が法人・団体である場合は、寄附金控除の対象となるかどうかも確認しておきましょう。
③ 契約書を作らないと後から無効になることも。高額な贈与(不動産など)は、契約書・登記などきちんとした手続きが必要です。
贈与は税制上の取り扱いが複雑で、また相続との関係など注意すべき点も多いので、贈与や相続に詳しい税理士に相談することを強くオススメします。
遺言書だけじゃない!「円満な遺贈」のための準備
~ 遺言書とあわせて検討したい3つの準備 ~
遺贈を希望される方に、当事務所では遺言書と併せて、以下の準備をおススメしています。
①:「え!受け取ってもらえない!?」を防ぐ準備
どの団体でも遺贈寄付を受け付けているとは限りません。団体によっては受け入れのガイドラインや専用窓口が整備されておらず、遺贈の実行がスムーズに進まないケースもあります。
また、遺言書に「全財産を◯◯団体に寄付する」と記していても、債務(借金)などがあった場合、その団体が寄付を辞退するケースもあります。
✅ 寄付先の団体に事前に意向を伝えて受け取ってもらえるか確認をしておく
✅ 財産や負債の状況を整理しておく
✅ 専門家を通して、実現可能な方法を選ぶ
②:「親族が反対してトラブル発生!?」を防ぐ準備
他の相続人から、反対意見が出てトラブルになることを防ぐために、「なぜ、その人(団体)に遺産を残したいのか」を自分の言葉で残せるエンディングノートの活用もおすすめです。
たとえば…
●長男の嫁には、闘病中の介護でお世話になりました。嫁は相続人ではありませんが、感謝を込めて、私の財産の一部を遺します。
●未来ある子どもたちの役に立てればという願いから、私の財産を子ども支援団体へ寄付することにします。
●長年の付き合いのある友人○○さんに、10万円を遺します。これまでありがとう。あなたの大好きな旅行に使ってね。
このような背景や気持ちを丁寧に書き遺すことで、他の相続人の理解を得られやすくなります。
※ただし、エンディングノートには法的効力はありません。法的効力がある「遺言書」と「エンディングノート」をセットで準備しておくことで、あなたの「“大切な人”に財産を遺贈したい」という願いが叶う可能性が高まります。
③:遺言内容を確実に実現するには「遺言執行者の指定」も有効
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言書の内容に基づいて、相続手続きや財産の分配などを実際に行う人です。
メリット
遺言内容の実現性(実行性)が高まる
→ 相続人同士が揉めたり、誰も動かなかったりするリスクを避けられる。
スムーズに遺言内容を実現できる
→ 相続人全員の同意を得なくても、単独で手続きができる(法律上の権限がある)。
相続人の手間や負担が減る
→ 専門家を遺言執行者にすれば、煩雑な相続手続きを安心して任せることができる。
一人では難しいときは、専門家へ
正しい生前対策の方法が分からない場合は、一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。
「困らない相続」がいちばん!
今回のコラムでは、法定相続人以外へ財産を遺したい時は、
「周囲の人に気持ちだけ伝えていれば大丈夫」というわけにはいかないこと、どのような対策をしておけば良いかをお伝えしました。
「家族がいないから団体に寄付したい」
「お世話になった人に財産を遺したい」
「自分の想いを、ちゃんとカタチにして遺したい」
そう気づいた今こそ、生前対策を始める絶好のタイミングです。
なかしま美春行政書士事務所では、遺贈寄付の専門家、贈与や相続に強い税理士、ファイナンシャルプランナー、各分野の専門家と連携し、“あなたの想いを実現する相続”をご提案しています。
「わたしのケースだと、どうなるの?」と気になった方は、まずは「現状の確認」からはじめてみましょう。
✨遺言書は、あなたの想いを未来に届ける魔法です✨
✨エンディングノートは、残される家族を笑顔にする魔法です✨
どうか手遅れになる前に、お早めにご相談ください。
「あれ?私の場合はどうなんだろ?」と気になった方へ
このコラムの執筆にあたり、一般社団法人 相続診断協会の「相続診断チェックシート」のチェック項目の一部を参考にさせていただきました。
「相続診断チェックシート」を使えば、ご自身の状況を診断することができます。
30個あるチェック項目に答えるだけで、ご自身の現状がわかり、「このまま何もしないと、何が問題になるのか」をあぶり出すことができます。
ご興味のある方は、「「相続診断チェックシート」診断希望」と、お気軽に当事務所までご相談ください(^^)