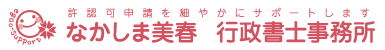あなたの「困った」を「相談してよかった」に変える行政書士・相続コンサルタントのなかしま美春です。
全33回のコラム、第8回をお届けします。
この連続コラムでは、「相続でトラブルになりやすいこと」、そして「今できること」について、わかりやすくお伝えしていきます。
このコラムが、相続について考える小さなきっかけとなり、
そして「家族で話す」「書き残す」という第一歩につながることを願って――
ぜひ最後までお付き合いください。
(全33回の一覧は>>こちら)
【連続❢相続コラム】第8回:「家族名義」で貯めているお金がある

写真はイメージです
「子ども名義の口座に、コツコツとお金を入れています」
「いつか孫にプレゼントできるように、孫名義の口座に貯金しているの」
「妻はずっと専業主婦ですが、妻の名義で預金を分けて管理しています」
このように“家族名義”でお金を管理している方、意外と多いのではないでしょうか。
けれども、“善意のつもりだった預金”が、トラブルの火種となることがあります。
今回は、「家族名義の預金」が原因で起こる相続トラブルと、その予防策を解説します。
口座の名義は“孫”でも、実際に管理しているのは“おばあちゃん”
たとえば、おばあちゃんが亡くなった時に、誰も知らなかった「孫名義」の通帳が出て来たとします。すると、この預金は「名義預金(めいぎよきん)」として扱われ、口座の中のお金は「おばあちゃんの相続財産」として扱われる可能性が出てきます。
名義預金とは?
「名義預金」とは、自分自身のお金を、家族や親族など別の人の名義で預金している状態のこと。
例えば、おばあちゃんが孫のために作った口座で、入出金もおばあちゃんが行っており、孫本人は口座の存在も知らない、あるいは全く関与していない…といったケースが該当します。
どんな問題が起こるの?
「名義預金」は、相続が発生したときに税務調査の対象となり、指摘を受けるリスクがあります。
そして、税務署が名義預金を「相続財産」と認定すると、過少申告加算税や、延滞税など、様々なペナルティ(追加負担)が発生する可能性があります。
また税務署だけでなく、他の相続人から
「そのお金は本当は誰のものなのか?」
という疑問が投げかけられ、相続手続きがストップしてしまうこともあります。
相続時のトラブルを防ぐために
こうした問題を防ぐには、まず「現状の確認」と「見直し」が重要です。
財産の名義を正しい形にしておく
さきほど述べたとおり、「名義預金」は、相続が発生したときに税務調査の対象となり、ペナルティの対象となるリスクがあります。
そのため、相続が発生する前に、「現状の確認」をし「見直し」をして、財産を“正しい姿”にしておくことが大切です。
✅推定相続人の確認
✅相続財産の全体像を確認
✅生前のうちに「誰のものか」を明確にし、必要であれば名義や管理方法を見直す
「財産は誰のものか」を明確にし、“正しい姿”にしておくことで相続トラブルを防止することができます。
一人では難しいときは、専門家へ
正しい生前対策の方法が分からない場合は、一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。
「困らない相続」がいちばん!
いかがでしたか?
「“家族名義”で預金しているから、私に何かあっても大丈夫」と思っていても、形式と実態が一致していないと“名義預金”とみなされ、かえって相続トラブルの火種となりえることをお分かりいただけたと思います。
「今のうちに整理し、“正しい姿”にしておくこと」が、未来の家族を守るカギになります。
「これって、名義預金になるのかな?」と気になった方や、
「今のうちに整理しておきたい」と感じた方は、ぜひお早めに専門家にご相談くださいね。
なかしま美春行政書士事務所では、贈与税・相続税に強い税理士と提携しています。どうぞお気軽にご相談ください。
「あれ?私の場合はどうなんだろ?」と気になった方へ
このコラムの執筆にあたり、一般社団法人 相続診断協会の「相続診断チェックシート」のチェック項目の一部を参考にさせていただきました。
「相続診断チェックシート」を使えば、ご自身の状況を診断することができます。
30個あるチェック項目に答えるだけで、ご自身の現状がわかり、「このまま何もしないと、何が問題になるのか」をあぶり出すことができます。
ご興味のある方は、「「相続診断チェックシート」診断希望」と、お気軽に当事務所までご相談ください(^^)