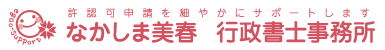あなたの「困った」を「相談してよかった」に変える行政書士・相続コンサルタントのなかしま美春です。全33回のコラム、第3回をお届けします。
この連続コラムでは、「相続でトラブルになりやすいこと」、そして「今できること」について、わかりやすくお伝えしていきます。
このコラムが、相続について考える小さなきっかけとなり、
そして「家族で話す」「書き残す」という第一歩につながることを願って──
ぜひ最後までお付き合いください。
(全33回の一覧は>>こちら)
第3回:相続人の中に長い間、連絡の取れない人は居ませんか?

(写真はイメージです)
「10年以上前にふらっと出て行ったきり戻ってこない兄がいます」
「両親が離婚してから会っていない妹がいます」
「息子は数十年前に海外に移住し、それ以降、住所や電話番号も不明です」
相続の現場では、こうしたご相談を受けることは決して珍しくありません。
けれど、相続が発生したときに相続人の中に連絡の取れない方がいると、相続トラブルにつながる可能性が非常に高くなるのです。
今回は、そんな「音信不通になってしまった親族がいる方」にこそ知ってほしい、相続の現実とその対策についてお伝えします。
“探し出す”ところから始まる「大変な相続」とは?
相続が発生すると、相続人同士で「誰が、どの財産を、どれだけ受け取るか」を話し合います。これを「遺産分割協議」と言います。
この協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。
つまり、相続の権利を持つ人が一人でも欠けていると、相続手続きは前に進みません。
この場合、相続手続きは「連絡の取れない相続人を探す」ことから始めなければならず、心身ともに、また金銭的にも負担が大きくなるケースが多くあります。
具体的にはどんな風に探すのでしょうか?
実例をご紹介します。
相続人の所在を調査
まずは戸籍の附票や住民票を取得して、所在を調査します。
※この調査を専門家に依頼することも可能です。
ただし、相続人が住所変更をしていなかった場合、役所の情報だけでは居場所が分からないこともあります。
戸籍の附票や住民票で相続人の所在を特定できない場合は──
A:警察に依頼、探偵を使うことも・・・
警察は「連絡が取れない」「家出している」といった理由でも「行方不明者届(捜索願)」を受理してくれますが、積極的な捜索が行われるとは限りません。
そのため、必要に応じて探偵や専門調査機関に依頼することもあります。
探偵は法律の範囲内で情報を収集し、行方不明の相続人の所在や連絡先を特定するノウハウを持っています。ただし、調査にかかる費用や期間が大きくなる場合もあり、依頼するかどうか、また業者選びについても慎重な検討が必要です。
B:失踪宣告
相続人が7年以上行方不明の場合、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることができます。
これが認められると、法律上その人は死亡したとみなされ、相続手続きを進められるようになります。
ただし、その後に本人の生存が判明した場合、失踪宣告は取り消され、相続も「開始していなかった」とみなされます。既に分配された財産は原則として返還しなければならなくなります。
また、相手の無事を願う気持ちから、申し立てをためらうご家族も少なくありません。
C:「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人が選任されると、その管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を進めることが可能になります。
※申し立てには専門的な書類の準備が必要なため、専門家(司法書士・弁護士)への相談をおすすめします。
相続税が必要な場合、ココにも注意!!
相続税の申告・納付には「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。
この期限を超えてしまうと、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。
遺産分割協議書の作成自体に法的な締め切りはありませんが、相続税申告や各種手続きのためには「10ヶ月以内」に協議を終えるのが実務上重要となっています。
「連絡の取れない相続人」がいる場合、残された家族にとって「10ヶ月以内」の期限も大きな負担となってしまいます。
対策方法は?
こうしたケースでは、「公正証書遺言」の作成を強くおすすめします。
「遺言書」と聞くと、自筆で書く「自筆証書遺言」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、私たち専門家が推奨するのは、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。
なぜ公正証書遺言なのか?
- 公証人が関与するため、法律上の不備や無効となるリスクがほとんどない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・滅失・偽造・変造の心配がない
- 全国どの公証役場からでも遺言の有無や作成場所を検索できる
- 遺言者の真意や意思能力が確認されるので、後から無効主張されにくい
- 相続人が協議できない場合でも、遺言の内容通りに財産分配が進められるため、遺産分割協議の長期化やトラブルを防げる
「公正証書遺言」があるだけで、“見つからない人を探すことなく”相続手続きを進められる可能性が格段に高まります。
遺言書を作成されるなら、作成時に費用はかかりますが、後の手続きがスムーズに進む「公正証書遺言」を選ぶことがポイントですよ。
「困らない相続」がいちばん!
いかがでしたか?
相続人の中に連絡の取れない方がいると、相続手続きが想像以上に大変になることが、おわかりいただけたと思います。
だからこそ、「元気なうちに、遺言書を残しておくこと」が、残されたご家族への最大の思いやりになるのです。
“連絡のとれない方を探すことなく”手続きが進められるよう、どうぞ早めの準備をしてくださいね。
すでにトラブルの懸念がある場合や、対策として公正証書遺言を検討している方は、ぜひ専門家にご相談ください。
「あれ?私の場合はどうなんだろ?」と気になった方へ
このコラムの執筆にあたり、一般社団法人 相続診断協会監修の「相続診断チェックシート」のチェック項目の一部を使用させていただきました。
この「相続診断チェックシート」を使えば、ご自身の状況を診断することができます。
30個あるチェック項目に答えるだけで、ご自身の現状がわかり、「このまま何もしないと、何が問題になるのか」をあぶり出すことができます。
ご興味のある方は、「「相続診断チェックシート」診断希望」と、お気軽に当事務所までご相談ください(^^)