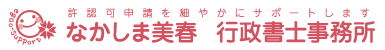あなたの「困った」を「相談してよかった」に変える行政書士・相続コンサルタントのなかしま美春です。全33回のコラム、第2回をお届けします。
この連続コラムでは、「相続でトラブルになりやすいこと」、そして「今できること」について、わかりやすくお伝えしていきます。
このコラムが、相続について考える小さなきっかけとなり、
そして「家族で話す」「書き残す」という第一歩につながることを願って──
ぜひ最後までお付き合いください。
(全33回の一覧は>>こちら)
第2回:相続人の仲が悪い!?

(写真はイメージです)
「うちの家族、仲が悪くて…」
「兄とは何年も連絡を取っていません」
「相続の話なんて、とてもできる雰囲気じゃない」
こうした声を、私は日々のご相談の中でたくさん聞いています。
家族の関係がうまくいっていても、相続を発端にトラブルが起こるケースは多いもの。
それなのに、そもそも「関係がうまくいっていない」場合、相続が終わるまでに何年もかかってしまうトラブルに発展したり、家族の仲が修復できないほどこじれてしまう、という事もありえるのです。
その理由は、相続の中で行われる「遺産分割協議」に関係しています。
「遺産分割協議」とは、相続が発生した後に、相続人同士で「誰が、どの財産を、どれだけ受け取るか」を決める話し合いのこと。
この協議を進めるためには、相続人“全員”の合意が必要なんです。
…つまり、誰か一人でも「納得できない」と言えば、相続手続きが止まってしまうのです。
それなのに冒頭に挙げたように、家族が不仲のままで相続を迎えてしまったらどうなるのでしょうか?
今回は、そんな「家族間の関係がうまくいっていない方」にこそ知ってほしい、相続の現実と対策について、わかりやすくお伝えします。
話し合いがまとまらない場合は?
まずは、相続人全員の同意が得られず、「遺産分割協議」が成立しないとどうなるかを説明します。
先ほども書いたとおり、相続人同士の「話し合い」つまり「遺産分割協議」で合意ができなければ、相続手続きを進めることができません。
そこで──
❶ 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て
調停では、中立的な裁判所の調停委員が相続人それぞれの主張を聞き、合意形成を目指して助言や提案を行います。
この調停はあくまで話し合いによる解決を目指すもので、相続人全員の合意が必要です。
ここでもまとまらなければ──
❷ 「遺産分割審判」の手続きに移行
審判では、裁判官が法律や事実関係を踏まえて遺産の分割方法を決定。相続人には、その内容に従う義務が生じます。
❸審判の結果に不服がある場合
2週間以内に高等裁判所へ「即時抗告」が可能です
このように話し合いで解決できない場合、最終的には裁判所の調停・審判手続きを通じて決着を図ることになります。
ただし、ここで注意しておきたいのが、この家庭裁判所の手続きには「時間」も「手間」も「お金」もかかるということ。
解決までに何年もかかるケースもあり、経済的にも精神的にも大きな負担となり、相続人同士の仲がさらにこじれてしまうことも非常に多いんです。
対策方法は?
実は、こうしたトラブルを未然に防ぐ方法があります。
それが──
「想い」を込めた遺言書を残しておくことです。
私がいつもおススメする「遺言書」は、家族をもめごとから守る「愛情のカタチ」として、とても有効です。
なぜ遺言書があるとスムーズになるの?
❶ 遺言書の内容に従って手続きが進められる
相続人全員の合意がなくても、遺言書があれば原則としてその内容に従って相続手続きを行うことができます。つまり、話し合いがまとまらなくても大丈夫なんです。
※ただし、相続人全員で合意をした場合や遺留分など例外もあるため、個別の事情は専門家に相談するのが安心です。
❷ 親の意思として受け止めやすい
「お父さん(お母さん)がこう書き残しているなら仕方ないね」と、相続人が納得しやすくなります。
❸ 感情的な対立の“火種”を減らせる
「どう分けるか」でもめるのではなく、「どう受け取るか」に意識が向くことで、争いを避けやすくなります。
❹特に「公正証書遺言」の作成がおススメ!
公証人が関与するため、法律上の不備や無効となるリスクがほとんどありません。
遺言書を作成されるなら、作成時に費用はかかりますが、後の手続きがスムーズに進む「公正証書遺言」を選ぶことがポイントです。
想いのこもった遺言が“争族”を防ぐ
遺言書に、自分の想いを込めた「付言事項(ふげんじこう)」を添えると、さらに効果的です。
付言事項とは、法的な効力はないものの、遺言者の「想い」や「背景」を自由に伝えられる文章(手紙)です。
たとえば…
- 「長女には現金を相続させます。これまで私の通院を助けてくれたことに感謝しています」
- 「次男には障がいがあり心配しています。他のみんなにはすまないが、多めに残すことを理解してほしい」
- 「私は良い親では無かったけれど、皆が穏やかに過ごしてくれることを心から願っています」
私自身、こうしたメッセージが相続人の心をやわらげ、兄弟姉妹の関係をやわらげてくれるケースを見てきました。
「困らない相続」がいちばん!
いかがでしたか?
親御さんは自分が亡くなった後こそ、「子ども達には仲良く助け合って暮らしてほしい」と願われているのではないでしょうか?
だからこそ、相続の専門家と一緒に、“想いのこもった遺言書”を作っておくことが、ご家族への最高のプレゼントになります。
すでにトラブルの懸念がある場合や、対策として公正証書遺言を検討している方は、ぜひ早めに専門家にご相談ください。
「あれ?私の場合はどうなんだろ?」と気になった方へ
このコラムの執筆にあたり、一般社団法人 相続診断協会の「相続診断チェックシート」のチェック項目の一部を参考にさせていただきました。(相続診断協会さん、いつもありがとうございます!)
この「相続診断チェックシート」を使えば、ご自身の状況を診断することができます。
30個あるチェック項目に答えるだけで、ご自身の現状がわかり、「このまま何もしないと、何が問題になるのか」をあぶり出すことができます。
ご興味のある方は、「「相続診断チェックシート」診断希望」と、お気軽に当事務所までご相談ください(^^)